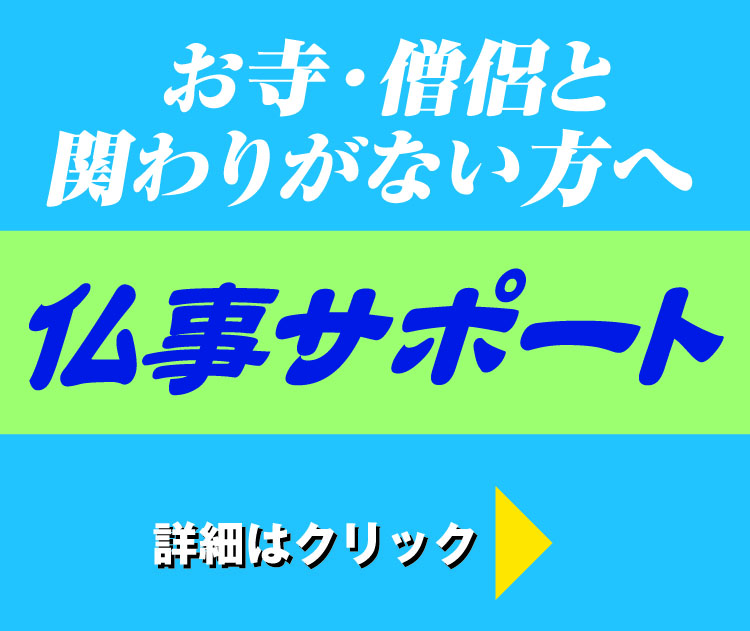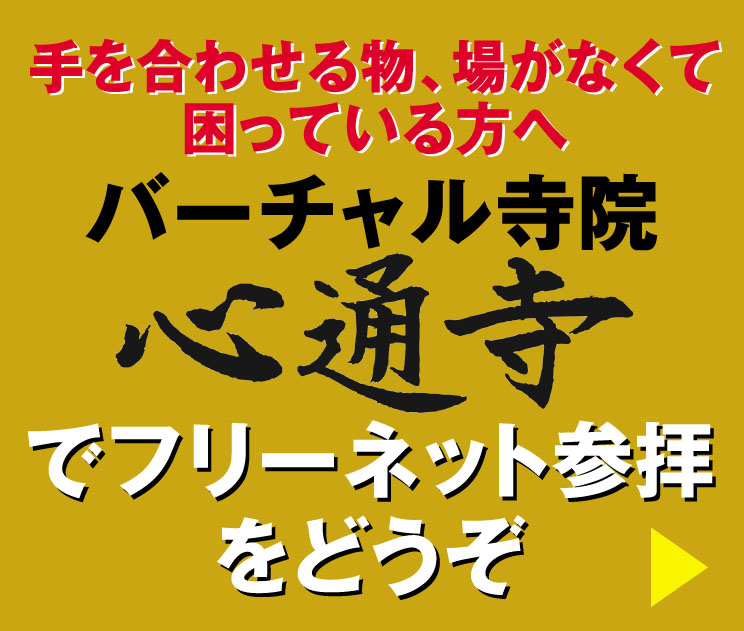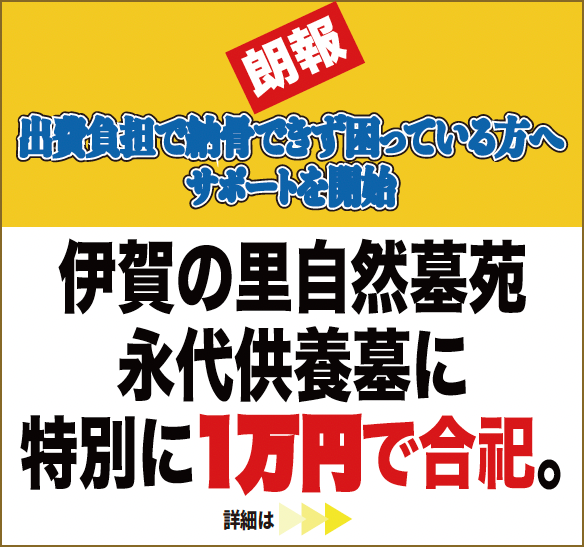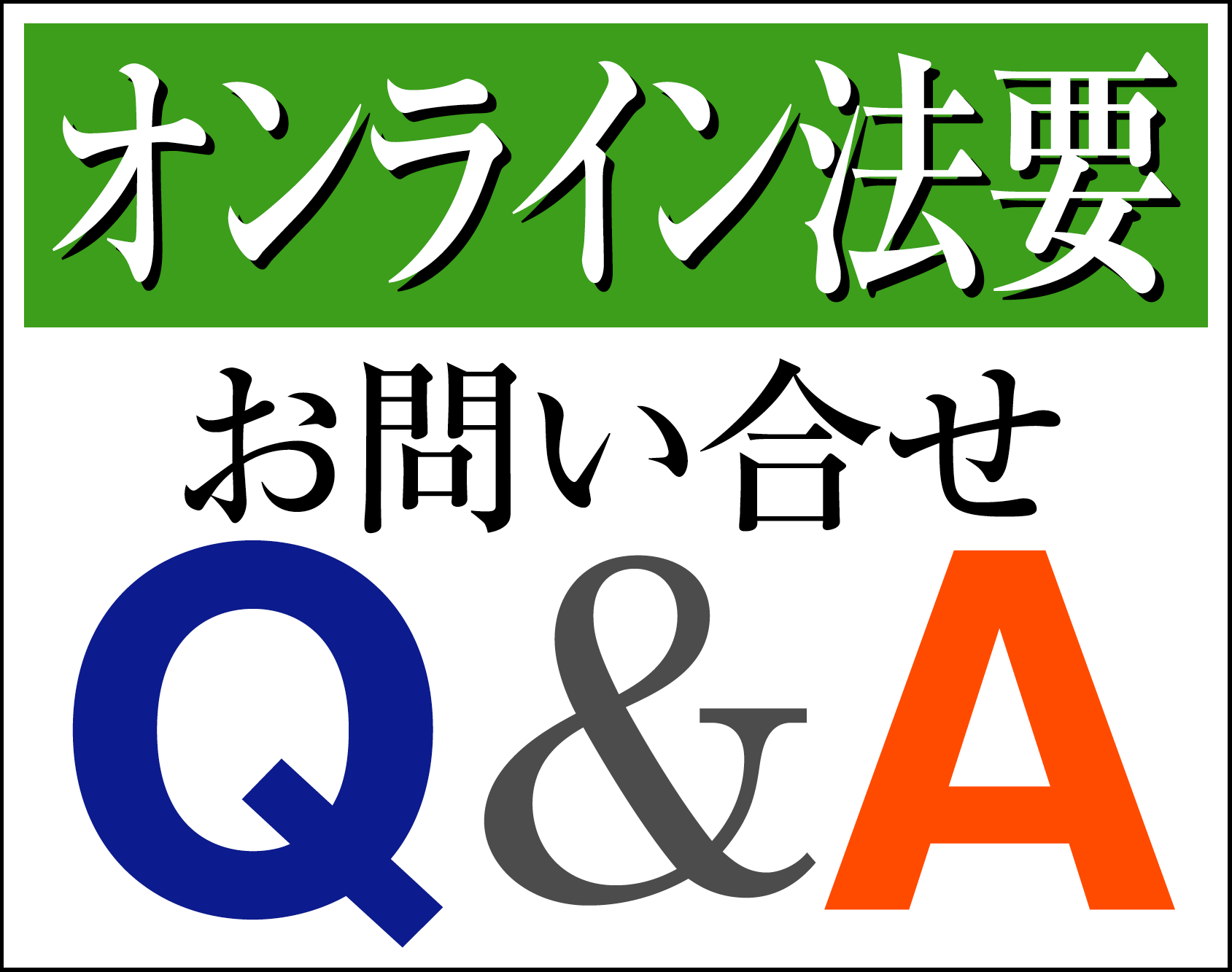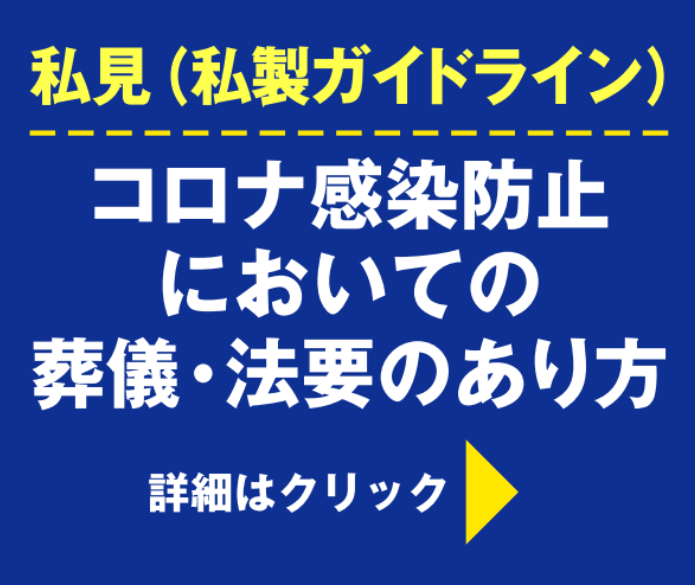小原崇裕のブログ『相談よもやま話』
永代供養墓完全ガイド - 正しい理解から失敗しない選び方まで
こんな悩みを抱えていませんか?
・お墓にお金をかけられない、かけたくない
・ほかに引き取り手がない縁者の、お骨をかかえて困っている
・離縁した親のお骨を、突然引き取ることになり困っている
・人に迷惑をかけないように生前に自分のお墓を考えておきたい
・生前に死後の心配を解消して、残りの人生を謳歌したい
・先祖代々のお墓を守るのが負担になって困っている
・先祖代々のお墓があるが、檀家門徒であることが負担になっている
・お寺の檀家になりたくない
・お寺とのつき合いはこりごり、檀家門徒をやめたい、寺離れしたい
・お墓が遠くにあり、なかなかお墓参りにいけない
・遠方へのお墓参りが年齢的・身体的・精神的に負担になっている
・今のお寺の住職、あるいは代替わりした新しい住職とは上手くやっていけない。お寺から離れたい
・故郷や遠方にあるお墓を近くに移したい
・宗教や宗派にこだわりたくない
・伝統的なお墓の制度、あり方にこだわりたくない
永代供養墓の正しい理解
まずは私が22年間続けてきた無料仏事相談において、15年くらい前までは「永代供養」という言葉を口にする相談者は皆無でした。せいぜい「納骨」という言葉ぐらいでした。当然、永代供養墓についてわかっている人も全くいませんでした。
私がいろいろと聞いていくと、「お墓がない」「お墓を持つことができない」ということで、納骨すべきお骨が手元にあり困っているという、檀家寺、菩提寺のない人からの相談でした。ですから、まさに永代供養墓が救世主となったのです。
その頃の永代供養墓のニーズとしては、先祖代々墓(家墓)もなく、新たにお墓を持ってもお墓を守る人、承継者がいない人が永代供養墓を求めるしかない状況でした。
10年前ぐらいからは、お墓の引越し、つまり改葬が増え始めました。と同時に、永代供養墓のニーズとして、「子供にお墓のことで面倒や負担を残したくない」という親心が増えてきました。
今では、永代供養墓の申し込みの半分ぐらいが生前申込で、子供に負担を残したくないという親の生前申込が主となっています。「墓じまい」が浸透し改葬は今でも増え続けています。その墓仕舞いの改葬先として永代供養墓が多いです。
「永代供養」の本当の意味
まず、「墓じまい」、「改葬」において一般の相談者が言う、「永代供養を考えている、したい」の「永代供養」とはどういうことなのかです。
お墓においての「永代供養」とは、墓守、お墓を継ぐ者がいないから、①お墓はそのままでお寺に墓守を引き受けてもらう、②今のお墓を墓じまいしてお骨は永代供養墓へ改葬、このどちらかを考えて、「永代供養」をしたい、考えていると言っているようです。
つまり、多くの方は仏教における本来的な「供養」ではなく、墓守り、墓参りのことを供養と考えて、お墓での供養をお願いする、永代供養墓に移すことで供養の心配がなくなる、ということを「永代供養」だと考えています。
「永代」が意味するもの
- 期限のない約束 -
「永代」とは、「期限がない」お寺(お墓)がある限り「ずっと」ということです。そのお墓がきちっと管理されてある限りずっと、管理者であるお寺がある限りずっとということを意味します。
お骨安置されているお骨が一定期間後合祀されても、供養が終わるわけではありません。また、最初から合祀だと「故人に申し訳ない」などでためらう人が少なくないですが、仏教においてお骨に霊が宿るということはありません。ただし、儒教、神道においてはそうではありません。
要は、仏教においては合祀であったとしても供養において全く問題ありません。お骨に対して手を合わせるのではなく、諸仏となった故人を仏として敬い感謝して手を合わせるのですから、故人に通じるのです。仏様には、私たちの心はどこにいようとお見通しです。
「永代供養墓」という名前について
今となっては、名称も「永代供養墓」(えいたいくようぼ)が定着しましたが、この「永代供養墓」という名称が浸透し始めたのは15年前ぐらいからです。私自身、「永代供養推進協会」という名で当NPO法人を立ち上げましたが、当初はどのような名でこのようなお墓が定着するのか見守っていました。
なぜかと言いますと、「永代供養墓」は、他の人のお骨と一緒のお墓に納骨、埋葬されることから、「合葬墓」「合同墓」「共同墓」「集合墓」とも呼ばれているからです。
そしてこの数年前から「樹木葬」と言われるお墓が人気となっています。本来樹木葬というのは、墓石の代わりに樹木を植えたかたちのお墓でしたが、今は永代供養墓=樹木葬として注目され人気となっています。
「シェア墓」としての永代供養墓
「永代供養墓」は、墓守り、お墓参りができなくても、たくさんの人がお墓参りすることで大切な故人が納骨、埋葬された場所であるお墓が護られるお墓=シェア墓と言えます。お墓の管理はお寺が責任を持ってしてくれるお墓です。
「供養」はお寺にお任せではなく、いつでも、どこでも、使用者である遺族縁者すなわちお参りする人がすることなのです。
そういうことからしますと、「合同墓」「共同墓」「合葬墓」の言い方が的確かと思います。私は説明するときには「シェア墓」の言い方をしています。
仏教における「供養」の本質
仏教では、仏・法(仏の教え)・僧を三宝として、敬い感謝して施します。仏教の最大の目的は、「往生成仏」(後生は仏様に救われ、仏土=浄土に生まれ往き、仏になる)することで、「生まれて死ぬ」という生死(しょうじ)の繰り返し(輪廻(りんね)転生(てんしょう))から、苦の一切ない安楽、区別、差別、分別のない平等、死もない不滅、永遠の世界に生まれ変わり、仏になることです。
この諸仏になれた故人に対して、生前の遺徳を偲ぶとともに、仏として教えをはたらきかけ見護ってくださっていることに敬い、感謝するのが供養です。
「永代供養墓」とは、お寺が永代にわたって供養と管理をしてくれるというお墓というのは正確ではありません。供養はお寺だけに任せるわけではありません。たくさんの人のお参りによって、その永代供養墓に納骨、合祀されている全ての故人に対する供養がされるお墓なのです。
自分にとって大切な人の供養は「仏様として敬い感謝の心」なのです。その心でお墓の前でなくても、お寺の本堂でなくても、仏壇の前でなくても、どこにおいても自分が今ここで、生前を偲び、その心で手を合わせる、拝むことが供養になります。この供養に期限など存在しません。
永代供養墓の納骨・埋葬方法
永代供養墓における納骨・埋葬方法は主に以下の2つがあります。
お骨安置タイプ
お骨安置スペース(棚等)にお骨を骨壺のまま、あるいは収容器に収めて安置します。最初から7寸骨壷から3寸骨壷に入れ替えて、収まらないお骨を合祀にする場合もあります。17回忌、23回忌、33回忌後などの一定期間後に合祀するかたちの永代供養墓が多いです。
一定期間後合祀されると、そこで「供養が終わってしまう」「永代ではない」など思われる方が多いですが、決してそんなことはありません。そのお墓そのものを皆で墓守りしていくわけで、合祀されたからと言って供養が終わるわけではありません。
永代供養墓の造りと納骨方法は造りや納骨方法にはさまざまな形式がありますが、基本的構造は変わりません。
お墓の地面から上の部分、地上部分のお墓の中にお骨を安置するスペース、そして表に参拝スペースが設けられ、石像を安置、花立てや焼香炉を設置、故人名などが刻字される墓誌を設置、 地面からお墓の下の地中部分に合祀スペースが設けられているというのが基本的構造です。
合祀タイプ
最初に骨壺からお骨を出して、他の人のお骨と合祀スペースに合葬します。粉骨にして合祀する場合もあります。
「合祀墓」という場合は、お骨安置タイプはなく、合祀タイプのみのお墓です。ほとんどの永代供養墓はお骨安置と合祀タイプの両方があります。
納骨方法の種類と特徴
①合祀スペースには、最初から骨壺のお骨を取り出して納める。(お骨を粉骨にして布袋に入れて納める場合もある)
②お骨安置スペースに、㋑持参した骨壺のまま、㋺三寸壺に入れかえ、入り切らないお骨を合祀スペースへ、㋩特定の収容器に入れかえて、などのかたちで安置。基本的には、合祀で埋葬、お骨安置で納骨される。
永代供養墓の費用内訳を理解する
次に、永代供養に関する費用の内訳についてご説明いたします。
基本料金の3要素
永代供養墓の基本的な一式料金は
①「永代供養料(供養・管理料)」
②「納骨料」
③「刻字料(墓誌あるいはプレートに故人名などを刻字する費用)」
が、 永代供養墓を使用するに当たっての基本料金となります。
申込時に一式料金を納めますが、お寺によって一式料金の内容が違いますので、必ず内訳を確認、そして別途料金の確認は必要不可欠なことです。
別途かかる費用と確認ポイント
別途かかる費用として何か。 納骨時に読経、納骨法要をお願いする場合のお布施は含まれているのか。 別途だとすると、お布施はいくらか。といったことを確認することが大切です。
注:何か特別なことをお願いしない限り、その分の別途料金が発生しないという 一式総額はいくらかを必ず確認する必要があります。
お寺によっては、刻字料が別途扱いとなっているところもありますので注意してください。 注:要は、納骨時に納めなければならない必要総額がいくらかです。 たとえば、1体20万円ということであれば、納骨法要、読経は含まれているのか、刻字料も含まれているのかの確認です。 含まれていないとすると別途料金はいくらか。 中には、納骨料も別途というところもありますので、とにかく、お骨を持参して納骨してもらうまでにいくらかかるのか、総額と内訳を確認することです。 そして読経、納骨法要をしてほしいという場合は、このお布施が含まれているのか、別途いくら納めればいいかを必ず確認することです。
予想外の出費を防ぐために
注:不明なこと、知りたいことは必ず理解できるまで聞くことです。わからなくて当たり前ですから、気兼ねや遠慮することなく、聞く、確認することが永代供養墓選びで大事です。 親身に教えてくれないようなところは選ばないほうがいいでしょう。
・お骨を納骨まで一時的に預かってもらう場合
・納骨法要後、食事等での部屋を使わせてもらったり、食事の手配等をお願いする場合の費用
・お花の用意をお願いした場合のお花代
等々、お願いしたことについての費用も必ず確認しましょう。
永代供養墓の7つのメリット
1. 無縁仏にならない
お参りは自由にできますが、お参りができなくても、納骨、埋葬した遺骨が無縁仏になることがありません。
2. 追加費用がかからない
申込時の所定の「一式総額料金」を納めれば、その後特別なことをお願いしない限り費用はかかりません。年間管理費(又は護寺会費)等一切かからないのが特徴です。
3. 費用が比較的安い
一体(生前の場合はお一人)でいくらの料金設定なので、普通のお墓を建墓するときに墓石代、建墓工事費、墓地の永代使用料がかかるのと比べると、費用としては安いです。
ただし改葬等で、お骨の納骨数が多くなると、特にお骨安置タイプだと安くなると言えない場合もあります。その場合は、没後年数が長いお骨、あるいは近親者でないお骨を合祀タイプにする、とても古いご先祖のお骨は、「〇〇家先祖代々」と一体にひとまとめするなどして、費用を落とすことを提言しています。
4. 宗教・宗派を問わない
使用申込者及び納骨される故人の宗教、宗旨宗派は問われません。
5. 生前申し込みが可能
生前に申し込みができます。
6. 縁者でも申し込み可能
故人の身内が全く不在などの場合、縁者でも申し込みができます。
7. 檀家になる必要がない
檀信徒、門徒になる必要がありません。行事への参加、寄付金などは強制されません。永代供養墓の合同法要も強制されず希望参加です。
最大の特長
最大の特長は、墓守り、承継する必要がないことで、お墓参り、お寺とのつきあいなどの面倒、金銭負担が後に残らないことです。
ですから、「墓守りがいなくなる、お墓参りをする人がいなくなる、お墓を継ぐ人がいない」などだけではなく、「子供や孫に、お墓のことで面倒や負担を残したくない」というニーズに応えるお墓です。そんなことで、息子さんがいらっしゃるご夫婦の生前申込が少なくありません。
永代供養墓に関してよくある誤解
デメリットを取り上げている解説が見受けられますが、私はデメリットというものはないとしています。なぜならば、永代供養墓を選ぶということは、目的、ねらいがはっきりしているからです。
1. 合祀にするとお骨を取り出せない
これは当然のことで、そのような納骨(埋葬)方法が合祀なのです。先々違うところに改葬できないのは、費用を抑えるために合祀タイプを選ぶなど承知のうえなのです。
お骨安置タイプを選んでも、ほとんどの永代供養墓の使用規則では納骨後のお骨の引き取りは不可となっています。私が関わって永代供養墓選びをした人で、先々お墓を建てたときにお骨を移したいからとお骨安置タイプにしたケースがありましたが、その後どなたも10年以上経っても改葬の気配もありません。
2. 家族・親族の理解が得られない
永代供養墓そのものの理解が得られないよりも、墓じまい、改葬することに理解が得られないことがあり、永代供養墓について正しく知ってもらえば理解は得られるのです。
3. 最終的に合祀される
確かにほとんどの永代供養墓はお骨安置タイプでも一定期間後合祀にするかたちになっていますが、ずっとそのままお骨安置する永代供養墓もあります。
やたらと合祀というものを供養にならないとしていますが、仏教においてそんなことはありません。むしろ、お骨にこだわるのは儒教で仏教においてのお墓にお骨安置する歴史としては新しいのです。いずれにしても、合祀だと供養にならないということはないのです。「合祀で故人に申し訳ない」など思ってしまうのは思い込みと言えます。
4. 納骨数が多いと割高になる
1体いくらという料金設定ですから、数が多くなると高額になるのは当然です。デメリットということではありません。
私が関わったケースで、10体の永代供養墓への改葬がありましたが、前述のように古いご遺骨を〇〇家先祖代々として1つにまとめて1体分するなどして費用を抑えるなど提言しました。墓じまいして改葬の場合、ほとんどが多くても5体までです。
5. 一般的なお参りができない
永代供養墓はいつでも自由に普通のお墓と同じようにお参りができます。自由にお参りができない永代供養墓は選ぶべきではありません。
また、自分たちのお墓にお参りしたという実感が得にくい場合があるというのがデメリットとしてあげられていますが、果たしてそうでしょうか。私は数千人の永代供養墓を選んだ方と接してきましたが、誰一人として、そのように感じている方はいません。むしろ、たくさんの方に手を合わせてもらって故人も淋しくなく喜んでいると、自分も拝んでいて気持ちがいいと言っています。
いずれにしても、先祖代々墓等従来のお墓とは、明らかに役割、ニーズが違いますので、ニーズによって選ぶわけですから、デメリットというものはないのです。要はニーズに合った永代供養墓をいかに選ぶかなのです。
失敗しない永代供養墓選びのポイント
永代供養墓選びは、一般のお墓(墓地購入)とは全く違う。 永代供養墓は、一般のお墓のように、墓地の区画の使用権利を得るためのお寺に永代使用料(永代とは放棄しない限りずっと)を納め、石材店から墓石を購入、建墓工事費の代金を払うというのとは全く違います。 お寺が建墓したお墓の墓守り(管理・供養)を永代にわたり(永代とはお寺、お墓がある限りずっと)任ってもらうもので、墓石など物を購入するのとは全く違うのです。
注:その任務を承るのはお寺、つまり住職(お寺によっては副住職が専任者としている)です。となると、ポイントは住職との面談です。
お寺の永代供養墓と霊園の永代供養墓の違い
私はこのNPOを創設依頼、墓地の管理者としてお寺が安心ということでお寺の永代供養墓選びについてサポートしてきました。一般の法人だと倒産が心配、過疎地以外(永代供養墓の運営が成り立つ)のお寺は、滅多に廃寺になることはないという考えからでした。 しかし5年ぐらい前から、民営霊園での僧侶としてのお勤めを知人筋から依頼されるようになり、考えが少し変わりました。霊園でもしっかり経営されているところがあり、管理も行き届いており、参拝者がとぎれることがない光景を目の当たりにして、こうした霊園の永代供養墓なら選んでも心配ないと思うようになりました。 逆に、管理の面、参拝者の賑わいにおいては、普通のお寺より良く感じます。 問題は霊園選びですが、それなりの規模で管理事務所、法要室、休憩所、トイレ等の完備、墓所の整備、管理が行き届いている、スタッフの対応が良い、そして参拝者が多いなどが感じられる霊園であればいいのではと考えていいと思っています。
住職との面談で確認すべきこと
住職の永代供養墓に対する姿勢、考えを確認することが大事です。 「お寺のこと、仏教のこと、わからないから何を話したらいいかわからない」という人が少なくないのですが、檀家、門徒でない限り、皆一般の人は仏教のこと、お寺のことを理解している人は少ないのです。永代供養墓について、確認すべきこと、気になること、何でも聞けばいいのです。わからないままにしているので、必要なことは全て理解しないと正しい判断ができません。
注:住職等僧侶との接し方
仏教において僧侶は、三宝とされている仏・法(仏の教え、仏法)・僧(仏様へのお取り次ぎする)の僧で、感謝として施される僧でありますが、江戸時代は「僧」は寺社身分でしたが、身分制度で今も生きているのは「皇族」だけで、江戸時代のように身分として保証されているわけではなく、今の時代は、お仕事、職業としての僧侶です。 つまり、住職も私たち同様の人間なのです。 ですから、マナー違反でない常識ある態度、言葉づかいで、接すればいいのです。 親身に対応してもらえなかったとなれば、そのお寺を選ばなければいいのです。 親身に面談してくださるお寺、つまり住職はいらっしゃるのです。 後述する、チェックリストに基づいて聞いていけばいいのです。
※お寺に見学、面談で出向く時にアポなしで行く人がいますが、それはダメです。 相手がお寺といえども、社会常識のようにアポをとっていくべきです。
見学時の確認ポイント
ただし、アポの電話の時に用件を聞かれ、簡単な説明を受けてしまう場合があっても、必ずお寺に足を運び、永代供養墓・境内・本堂の見学と面談をしてください。 必ず、①電車等交通利用の場合は最寄り駅から歩いて、②車の場合はアポの段階で駐車場の確認をして、お寺に出向いて、永代供養墓を案内してもらい、参拝スペース(香炉・花台)、納骨スペース(お骨安置・合祀 )、墓誌の確認、⑴心静かに手を合わせられるか、⑵お参りにきていることが感じられるか、⑶手入れがされているか、どのように感じるかです。
そして墓地、境内の手入れがゆき届いているかもしれません。それから、本堂も拝見すべきです。本堂に案内されたら必ずご本尊に手をあわせてください。快く手をあわせてみて心静かに快く手をあわせたいと感じるでしょうか、心静かに拝めるということが大事です。こんなことも検討する上で参考にしてください。
チェックリスト23項目
さて、一番大事な住職との面談での確認です。 チェックリスト風に項目を挙げます。
①料金は一式総額でいくらか。そして、一式の内訳。要は、納骨まで完了するに当たっての総額かどうか。別途料金となっているのは何でいくらか。
②納骨場所(お墓に案内された時にその場で確認すべきです)。
③お骨安置での場合、そのままずっと安置されるのか、一定期間後に合祀されるのか。その場合の一定期間とは。
④お骨安置の場合、現在の骨壺のままか、それとも骨壺、収容器、サイズが変わるのか。
⑤お参りは、お寺に声をかけず自由にできるのか。
⑥参拝時間は決まっているのか。
⑦俗名のままで可能か。
⑧戒名・法名をつけてもらうことは可能か。その場合のお布施はいくらか。
⑨故人あるいは使用申込者の宗教・宗派を問わないか。
⑩すでにつけた戒名・法名で受け入れてもらえるか。
⑪檀家、門徒、信徒になることが条件になっていないか(なるのが条件の場合は永代供養墓とは言えません、やめたほうがいいです)。
⑫お彼岸やお盆などに合同法要があるのか。その場合、参加を強制されないか。参加する場合のお布施はいくらか。
⑬生前申込みはできるのか。
⑭夫婦など同時に複数申し込む場合は割引になるのか。
⑮納骨法要は墓前なのか、本堂で行なわれるのか(お布施については一式料金と別途料金の確認時に)。
⑯納骨時に納骨法要と一周忌などの法要もあわせてお願いできるか。その場合のお布施はいくらか。
⑰回忌法要もお願いできるのか。その場合のお布施はいくらか。
⑱お寺で葬儀もお願いできるのか。その場合、葬儀社はお寺指定になるのか。こちらで他葬儀社に依頼していいのか。葬儀のお布施はいくらか。
⑲納骨するまで少しの間、お骨を預かってもらえるか。
⑳火葬後、その日または何日後とかに納骨できるか。
㉑位牌等、お焚き上げをお願いできるか。その場合のお布施はいくらか。
㉒納骨法要後、食事等で部屋を使わせてもらえるか。その場合、業者の食事の手配もお願いできるのか。
㉓分骨をしたものを持って帰りたいが、分骨をお願いできるか(証明書も必要)。
「永代供養墓」はこんな人におすすめ
・お墓参りできない、する人がいない(遠方、老齢のため)
・墓守りがいなくなる、いなくなった
・お墓を継ぐ人がいない、いなくなる(子供がいない、子供が嫁いでしまった、身寄りが遠方にいる)
・お墓のことで子供など残された家族に負担、面倒をかけたくない
・子供が身体不自由だから、自分たち夫婦と子供のお墓は今のうちに子供が困らないように決めておきたい
・身寄り、親しい縁者がいるが、全く付き合いもしてこなかったのでお墓のことで頼りたくない、頼れない
・身寄りもなく、独居している身なので、自分一人のお墓を求めている
まとめ
- 正しい知識で最適な永代供養墓を選ぶために -
永代供養墓は、この22年間で大きく変化してきました。当初は「お墓がない」「お墓を持つことができない」人のための救済策だったものが、今では生前申込による「子供に負担を残したくない」という親心からの需要が主となっています。
永代供養墓の本質は「シェア墓」であり、皆で墓守りし、供養していくことにあります。お寺が管理責任を担い、参拝者が供養を行うという役割分担があります。永代供養は期限がなく、お寺(お墓)がある限り「ずっと」続くものです。
合祀について多くの誤解がありますが、仏教においては合祀されても供養に全く問題はありません。お骨に霊が宿るという考え方は仏教にはなく、諸仏となった故人を敬い感謝する心が供養の本質だからです。
永代供養墓のメリットは、無縁仏にならない安心感、追加費用がかからない経済性、宗教・宗派を問わない柔軟性など多岐にわたります。最大の特長は、墓守り・承継の必要がなく、後世に負担を残さないことです。
多くのサイトでデメリットが取り上げられていますが、永代供養墓選びにおいては、目的やニーズがはっきりしているため、本質的なデメリットはありません。重要なのは、自分のニーズに合った永代供養墓を正しい知識をもって選ぶことです。
永代供養墓は、お墓参りができない人、墓守りがいなくなる人、お墓を継ぐ人がいない人、子供に負担を残したくない人など、様々な事情を持つ方に適したお墓の選択肢です。これからも増え続けるであろう永代供養墓の中から、正しい知識を持って、自分に最適な永代供養墓を選んでいただきたいと思います。